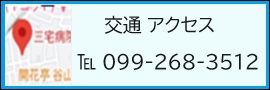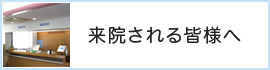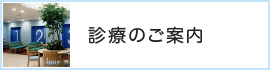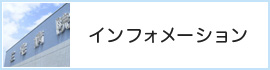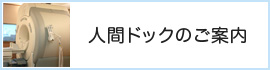院内感染対策指針について
- 院内感染対策に関する基本的な考え方
- 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本事項
- 院内感染対策に関する職員研修についての基本方針
- 感染症の発生状況の報告の対応に関する基本方針
- 院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 患者様に対する指針の閲覧に関する基本方針
- その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
- 感染防止対策チーム(ICT)の業務についての基本方針
1. 院内感染対策に関する基本的な考え方
病院における院内感染の防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは病院にとって重要である。このため院内感染防止対策を全職員が把握し、この指針に則った医療を患者様に提供できるよう取り組んでいく。
2. 院内感染対策のための委員会等の組織に関する基本事項
院内横断的な部署からの構成員で組織する「感染対策委員会」は毎月 1 回定期的に会議を開催して院内感染予防対策の策定と推進を行なっている。また、緊急時は、臨時に同委員会を開催する。
(所掌事項)委員会は次の事項を所掌する。
(所掌事項)
- MRSA・緑膿菌等、院内感染の報告
- 院内感染と思われる事例の調査と対策
- 構造設備と環境面の対策の立案と対応
- 職員教育・研修
- 各感染症サーベイランスの報告と対応
- 抗生剤の適切な使用方法の徹底
- 院内感染対策の指導の徹底
- 施設内外の感染症発生情報の収集分析、警戒警報の発令
特に新型インフルエンザ対応について
3. 院内感染対策に関する職員研修についての基本方針
- 院内感染の基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的に開催する。
- 全職員を対象とする研修(院内研修)を年2回程度開催する。また、必要に応じて随時開催する。
- 研修の開催結果または外部研修の参加実績を記録・保存する。
4. 感染症の発生状況の報告の対応に関する基本方針
院内感染の予防、蔓延の防止を図るため院内における感染症の発生状況を週 1 回毎に「サーベイランスレポート」として院内職員に周知するほか、必要な場合は紙面や院内メール(グループウエア)に掲載し情報の共有に努める。
5. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
感染症患者が発生した場合は担当医または看護主任または看護師長から感染対策委員会( ICC )に報告し、報告を受けたICTは対応・指示を行なう。必要に応じ臨時感染対策委員会を招集し感染経路の遮断及び拡大防止に努める。
届出義務のある感染症患者が発生した場合は、感染症法に準じて行政機関へ報告する。
6. 患者様に対する指針の閲覧に関する基本方針
この指針は患者様等に感染対策への理解と協力を得るため、院内掲示を行い閲覧の推進に努める。
7. その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染対策の推進のため「院内感染対策マニュアル」を整備し職員への周知徹底を図る。またマニュアルの定期的な見直しを行なう。
8. 感染防止対策チーム(ICT)の業務についての基本方針
ICTは以下の業務を行う
(ア)
感染対策チームは、1週間に1回程度(月1回は全体ラウンド)、定期的に院内を巡視し、院内感染事例の把握を行うと ともに感染防止対策の実施状況の把握・指導を行い、 ICT 会議で必ず各部署ごと報告を行う。また、院内感染事例、院内感染の発生率に関するサーベイランス等の情報を分析、評価し、効率的な感染対策に役立てる。院内感染の増加が確認された場合には病棟ラウンドの所見及びサーベイランスデータ等を基に改善策を講じる。巡回、院内感染に関する情報を記録に残す。
(イ)
感染防止対策チームは微生物学的検査を適宜利用し、抗菌薬の適正使用を推進する。バンコマイシン等の抗MRSA薬及び広域抗菌薬等の使用に際して届出制等をとり、投与量、投与期間把握を行い、臨床上問題となると判断した場合は、投与方法の適正化をはかる。
(ウ)
感染防止対策チームは院内感染対策を目的とした職員の研修を行う。また院内感染に関するマニュアルを作成し、職員がそのマニュアルを遵守していることを巡回時に確認する。